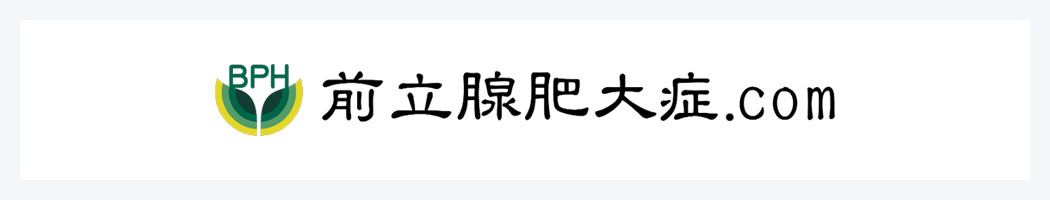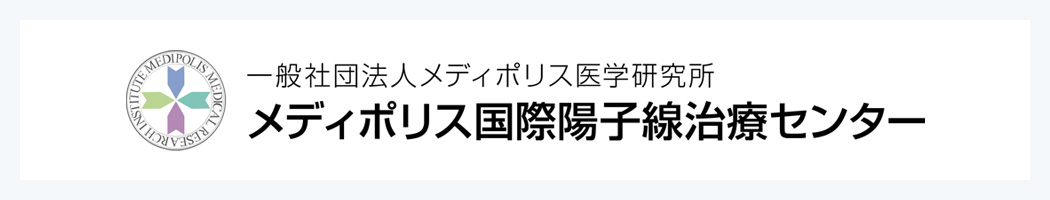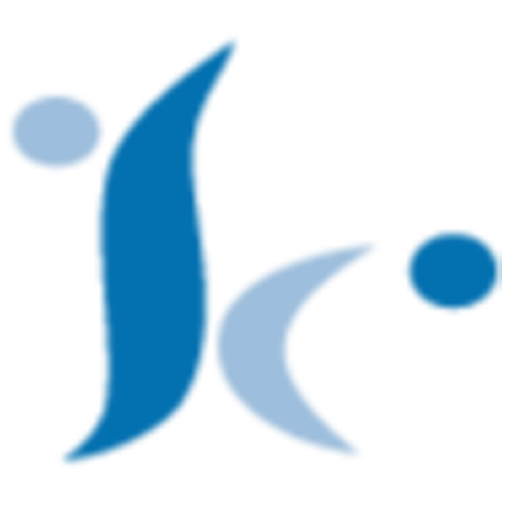STD(性感染症)について
1. STD(性病・性感染症)とは
性行為により感染する病気のことです。
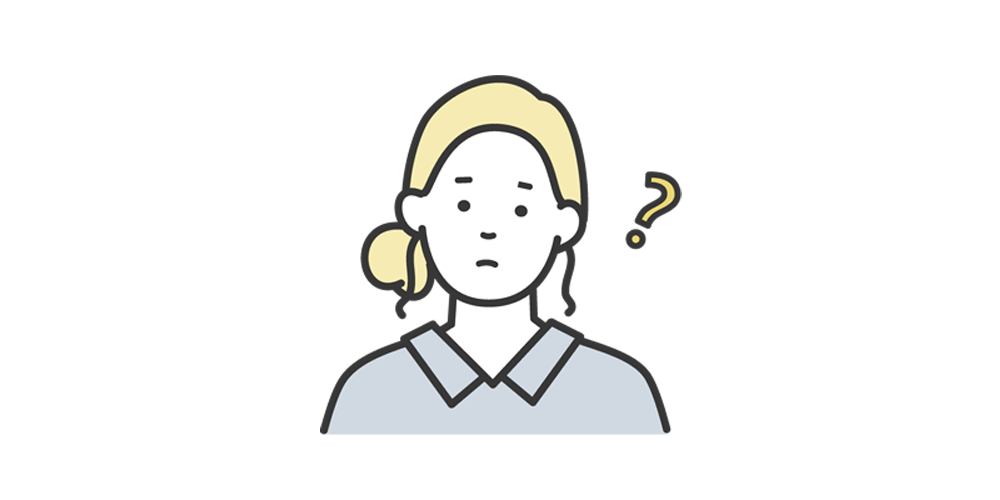
2. 誰にでも起こりえる病気です
「性病」というと、ひと昔前までは一般の人には関係ない、性風俗の病気というイメージでしたが、現在ではごく普通のカップル間でも広がっています。性感染症は、私たちの誰にでも関係のある病気なのです。
3. STDの感染経路
STDは性行為で感染し、性行為以外の日常生活では感染しません。

4. なぜSTDに気をつけないといけないの?
- 症状がでにくいSTDはパートナーに感染させる可能性があります。
- 症状がでなくても進行します。
- 男女ともに不妊の原因になることがあります。妊婦さんは流産や早産の原因になることもあります。

5. 子供に感染します
出産時に感染の可能性があります。こどもに感染すると肺炎や脳症、失明の原因になったり死に至ることもあります。
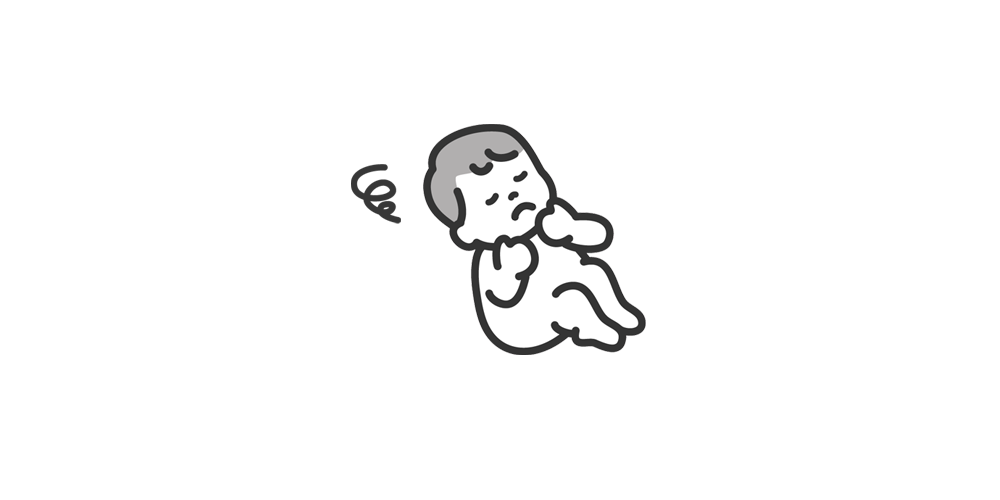
6. STDの予防はどうしたらいいの?
コンドームをつけることをこころがけましょう。コンドームで防ぎきれないSTDもありますが一番現実的で確実な予防方法がコンドームの着用です。
またSTDは、のどにも感染します。オーラルセックスが一般的になりつつありますが、 オーラルセックスからの感染が広がっていますので注意をしてください。
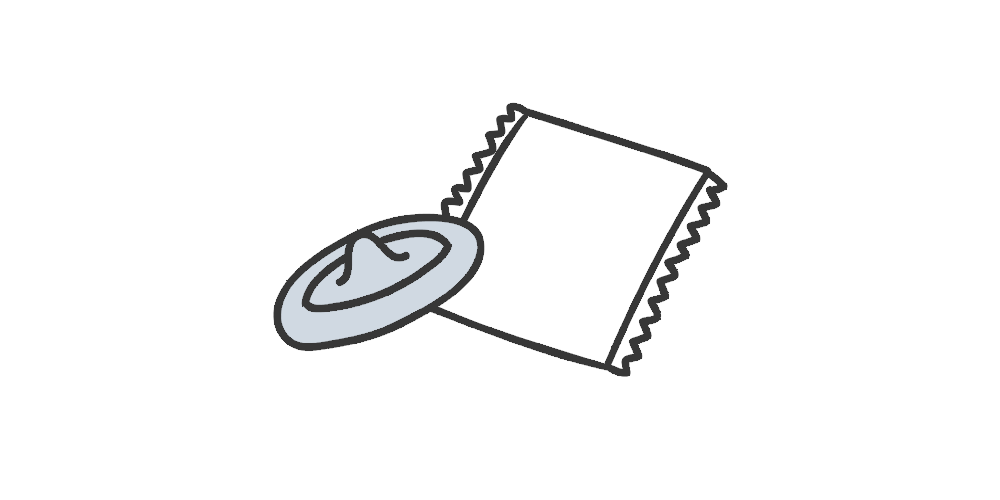
7. STDは自然治癒はしません
「気になることがあった・・症状はないけど・・・もしかしたら」「これって何の症状?」など、もしかしてSTDかもしれないと思ったら。放置せずに早い対応が必要です。
STD(性病・性感染症)の多くは、「症状を感じない」ことが特徴です。そして、STDは放っておいて自然に治ることは稀です。気になる症状があるときは受診をしてください。

淋病
正しくは「淋菌感染症」といいます。感染者との粘膜接触(オーラルセックスやコンドームなしのセックス)などで感染します。感染力が強く、男女ともに発症しやすい性病です。
症状
- 男性:排尿時の強い痛み、膿のような分泌物
- 女性:おりもの増加、不正出血、下腹部の痛み(自覚症状が少ないことも多い)
診断
尿検査や膣分泌物・のどのぬぐい液を用いた PCR検査 が一般的です。
治療
抗生物質(注射または内服)で治療します。最近は耐性菌が増えているため、適切な薬を選ぶことが重要です。保険診療で治療可能 です。
クラミジア
日本で最も多い性感染症。クラミジア・トラコマチスという細菌によって感染します。感染者との粘膜接触(オーラルセックスやコンドームなしのセックス)などで感染します。
症状
- 男性:排尿時の違和感、少量の分泌物
- 女性:おりもの増加、不正出血、下腹部痛
- のどや直腸に感染することもあります。
- 無症状のことが多く、気づかずにパートナーにうつしてしまうケースがよくあります。
診断
尿・膣分泌物・咽頭ぬぐい液などを用いた PCR検査。
治療
抗生物質(マクロライド系やテトラサイクリン系)を内服します。保険診療で治療可能 です。
梅毒
梅毒トレポネーマという病原体が侵入して感染します。潜伏期間は3~4週間程度なので血液検査は性交渉があってから3週間後以降に検査をし判定します。症状がなかなかでない潜在梅毒も多いです。近年、日本で再び増加しています。
症状
梅毒は治療しなければ、第1期、第2期、第3期・・・と段階的に進行します。梅毒には第1期~第4期までありますが、現在では1~2期までに治療をすることが多いので第3期4期までに進行するケースは稀です。近年増加傾向にあります。
● 第1期
感染後3週間~3ヶ月を第1期といいます。性器に無痛性のしこりが発生します
● 第2期
感染後3ヶ月~3年を第2期といいます。全身にバラ疹という特徴的な赤い発疹が手足の裏から全身に広がります。
● 第3期
感染後3年~10年を第3期といいます。皮膚や筋肉、骨などにゴムの塊のような腫瘍が発生します。
● 第4期
感染後10年以上を第4期といいます。この段階まで進行すると内臓や脳、神経や臓器に腫瘍が広がり死亡に至ります。
診断
血液検査で判定します。
治療
抗生物質(ペニシリン系)を用います。早期に治療すれば完治します。保険診療で治療可能 です。
ウレアプラズマ
ウレアプラズマは、性行為をきっかけに感染することがある小さな細菌の一種です。一般的な性病(クラミジアや淋菌など)に比べるとあまり知られていませんが、男性・女性ともに泌尿生殖器に症状を起こすことがあります。ウレアプラズマは主に性器に感染する細菌ですが、オーラルセックスなどでのどに感染することもあります。
症状
- 男性:尿道の違和感、排尿時の痛み、透明〜白っぽい分泌物
- 女性:おりものの増加、不正出血、下腹部の違和感
- 無症状で経過することも多いため、気づかないままパートナーに感染させてしまう可能性があります。
- のどに感染した場合
- のどの痛み、イガイガ感
- かすかな違和感、軽い咽頭炎様の症状
診断
尿や膣分泌物、のどの奥(咽頭)を綿棒でぬぐって PCR検査を調べます。
治療
抗生物質による治療を行います。
ただし、ウレアプラズマは通常の性病に使う抗生物質では効かない場合があり、検出後は適切な薬を選ぶ必要があります。パートナーも同時に検査・治療を受けることが大切です。
*現時点ではウレアプラズマ感染症は 保険診療の対象外 です。検査・治療は 自費診療となります。
エイズ
HIV(エイズウイルス)はヒト免疫不全ウイルスともいいます。
症状
HIV感染し治療をせずに数年~10年たつとだんだん免疫が低下し、健康な人であればなんでもない菌やウイルスで日和見感染をおこしさまざな症状や病気を発症します。
その状態が「エイズ指標疾患」にあてはまると「エイズを発症した」と診断されます。発症後の症状は多彩で原因不明の発熱、体重減少、下痢、カビによる肺炎、皮膚症状、寝汗など。
感染経路
HIVの感染経路は以下の3つがあります。
- 性行為
- 注射などを使用した血液による感染
- 母子感染
日本では性行為による感染が最も多いです。HIVウイルスは通常の社会生活で感染することはありません。HIVは空気に触れると死滅するウイルスです。
HIVウイルスを多く含むのは血液、精液(さきばしり液含む)、腟分泌液、母乳などの体液です。汗、涙、唾液、尿、便などの接触による感染の可能性はありません。
診断
- HIV抗体・抗原検査(血液検査) で確認します。
- 感染直後は検査に反映されない「ウィンドウ期」があるため、感染の可能性がある行為から 6〜8週間以降 の検査が確実です。
治療
- 現在は 抗HIV薬(ART:抗レトロウイルス療法) が確立されており、毎日の内服でウイルスを抑えることができます。
- 適切に治療を続ければ、エイズを発症せずに 健康な人とほぼ同じ寿命を保つことが可能 です。
ケジラミ※1
吸血性昆虫のケジラミが陰毛に卵を産み付け繁殖。
症状
成虫が血を吸うので男女ともに症状は発疹などなく寄生部分が痒くなります。
主に性行為で感染をしますが、まれに温泉やプール・サウナなどで感染も。虫は人体から離れても48時間は生存するので、寝具、シーツ、タオルなどで家族内に広がることもよくあります。
性器ヘルペス※1
ヘルペスの病変部(小さな水泡や発疹)と接触することで感染します。 口唇ヘルペスが性器に感染することは稀ですが、過去に事例はあります。
症状
性器ヘルペスに感染し、発症すると男性は亀頭部に水泡や発疹。女性は大陰唇に水泡ができて破れて潰瘍になると歩行も困難なほどの激しい痛みといった自覚症状があります。
ヘルペスは一度感染すると完治できない感染症なので発症させないように上手に付き合っていかねばなりません。胎児は経膣分娩で感染しヘルペス脳症に罹患することもあるので妊婦は注意してください。
カンジダ※1
よく「カンジタ」と間違われますが「カンジダ」です。
カンジダは厳密な意味での性感染症ではなく誰でも体内にもっているカンジダ真菌が病中病後、またはストレス過多で免疫が低下しているときに発症します。主に女性が発症しやすい感染症です。
症状
男性は生殖器が外にでているので真菌は繁殖しにくいのですが、通気性があまりよくない場合に稀に亀頭部にかゆみやただれが現れたり、水泡や白いカスのようなものがでてくることもあります。
女性は膣内で活発に活動しだし外陰部が赤く腫れ、排尿痛やかゆみなどの症状がでます。
尖圭コンジローマ※1
ヒト・パピローマウイルスが原因の性感染症で、「コンジローム」と呼ばれることもあります。
症状
男性は亀頭の周りの包皮に先のとがった大小さまざまなイボが多発し、重症になるとカリフラワー状のイボになります。女性は陰唇、膣口にとがった大小さまざまなイボが多数できます。
アナルセックスやハードプレイ愛好者で肛門周囲や直腸粘膜内にイボができてしまうこともあります。
感染してすぐにイボをつくるわけではなく潜伏期間が1ヶ月~1年と長いので感染源が特定しにくいです。非常に再発性が高く3ヶ月以内に30%は再発をすると言われています。
痛みもかゆみもないために放置をしてしまいがちですが、放置をするとどんどん増殖して排尿や射精が困難なるほどペニスを覆いつくしてしまったり、男性は陰茎癌、女性は子宮頸がんの原因になることもあります。
- 1:ケジラミ、性器ヘルペス、カンジダ、尖圭コンジローマは当院でも診察や治療ができますが皮膚科受診をお勧めします。